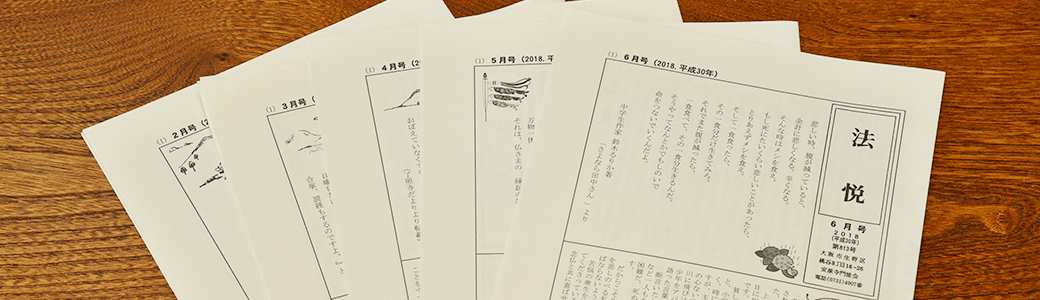2025.03.27ブログ
法悦 4月
法 悦4月号 895号
ハチドリのひとしずく
森が燃えていました。
森の生きものたちは、われ先にと逃げていきました。
でもクリキンディという名のハチドリだけは、
いったりきたり
口ばしで 水のしずくを一滴ずつ運んでは
火の上に落としていきます。
動物たちがそれを見て、
「そんなことをしていったい何になるんだ。」
といって笑います。
クリキンディはこう答えました。
「私は、私にできることをしているだけ」
青色青光
岩手県大船渡市で大規模な山火事が発生しました。何日も鎮火せず、
結局降雨を待たなければならなくなり、多くの山林や家屋が焼失しました。
特に東日本大震災の津波被害から、ようやく復興しつつあったところに、
このたびの山火事で二重に被災された方々もおられ、誠に痛ましい
ことです。
上記は南米アンデスに伝わる民話ですが、主人公のハチドリ
(英語名ハミングバード)は体長一〇センチにも満たない非常に小さい
鳥で、最小のマメハチドリなどは体重も2グラムしかなく、ホバリング
しながら花の蜜を吸って主食とし、その玉虫色の姿の美しさから
「飛ぶ宝石」とも言われています。
一度燃えさかると消すことの困難な山火事を、小さなハチドリの
くちばしからのひとしずくで、消すことなど到底かないません、が、
それでも自らに出来ることを精一杯尽くすその姿は、とかくどうせ
微力を尽くしたとて何も変わらないと諦める事を戒める物語です。
法蔵菩薩も師である世自在王仏から「あなたの立てた誓願は、大海の
水をすべて升でくみ取り、海底の宝を体をぬらさず手に入れるほどの
難事である。」と、諭されましたが、決して諦めず兆歳永劫のご修行
の末、ついに一切衆生を救わんという誓いを成就し、阿弥陀仏となられた、
だから我々はすでに救いに預かっているのだ、と説かれるのです。
住職日々随想
能登半島地震とそれに続く水害、大船渡の震災被害と山火事、
同じ地域を二度襲った災害に心痛みます。
まことに火も水も生活に不可欠なものですが、牙をむけば生活を根こそぎ
にしてしまいかねないものです。
七高僧のおひとり善導大師の「観経疏」に、『二河白道の比喩』が
あります。
善導大師はこの譬喩を通して、自らの人生を真に積極的に生き抜こう
とする決意が、いかなる状況にあろうとも、人間にとって何よりも大切な
ものであることを明らかにしておられます。
曰く、旅人がはるか西に向かって進み続けると、無人の茫漠たる広野に
到った。
すると忽然として眼前に、南に火の河、北に水の河が現れた。
それぞれ深さは底知れず南北両方にほとりはない、見ると中間に幅四、五寸、
長さ百歩ばかりの白い道が西の岸に続いている。
が、その道は時に火に焼かれ、時に水に飲み込まれ、と常に水火に侵され
ている。
そのうち後方から群賊や悪獣が、旅人を害そうとして追いかけてくる。
旅人は、引き返しても止まっても殺されてしまう、かといって前に進ん
でも水の河、火の河に落ちて死んでしまうだろう。
いずれにしても死は必定と、しばし逡巡した。
が「すでにこの道があるではないか」ならば前に進もう、と決意した
その時、東の岸から釈迦の「汝この道を行け、必ず死の難無けん」と
勧める声、また西の岸から「心を定めて恐れず直ちに来たれ。
我必ず汝を守護せん」と阿弥陀の呼び声が聞こえてきた。
ここに到って旅人は決然として、白道へ一歩踏み出した。群俗悪獣の
戻って来い悪いようにはせぬ、との声も振り切り、ついに西の岸、
極楽浄土に到り、善友と相まみえることが出来た、と。
慣用句に「怒りに身を焼く」「欲に溺れる」があります。
この二河白道の比喩で表される火の河は、衆生の瞋憎(しんぞう)・瞋恚
(しんに)(いかり・はらだち)水の河は貪愛(とんない)・貪欲(とんよく)
(尽きぬ欲望)を表しています。
怒りはカッとなって火が付き、燃えさかればついにはわが身をも焼き
尽くしてしまいます。
また水がじわじわとかさを増すように、むさぼりの心は、常にもっと
もっとと尽きることがありません。
じつに臨終の間際まで尽きることがないのが、この水火で表される
人間の根本煩悩なのです。
自らを省みる仏道に於いて、この根本煩悩と向き合い続けること、
それが念仏者の生活なのです。
真宗入門「お斎」
「お斎(とき)」とは、仏事の際にいただく食事のことを言います。
もともとは、古代インドで出家者が決まった時間(とき)に食事を
する事を「斎(とき)」と称していました。
これが後に転じて、仏事・法要などの折りにいただく食事どきに
「斎」の字を当てて、「とき」とよぶようになったのです。
歴史を遡ると、新たに僧侶になったときや、新しくご本尊や仏像を
お迎えしたときの法要で「お斎」が設けられてきた事が伺えます。
「お斎」は仏事・法要時の単なる会食でも宴会でもありません。
本願寺・第八代の蓮如上人は、日本全国を行脚し、布教に出向かれ
ましたが、お斎も大いに奨励されたということです。
上人はお斎を「合掌して如来・親鸞聖人の御用(おはらたき)として
いただく」とおっしゃっています。
仏祖のはたらきの中に生かされているという、そのご信心を
たしかめることにもつながる、「お斎」は大切な仏事のひとつなのです。
法語の味わい
ー法語カレンダー4月号よりー
天上天下唯我独尊
どうでもよい いのちはない
約二五〇〇年前の北インドで、お釈迦様はお生まれになられました。
誕生後すぐに七歩、歩かれ、天の上と下を指さし「天(てん)上(じよう)
天(てん)下(げ)唯(ゆい)我(が)独(どく)尊(そん)」と獅子吼されました。
その時に大地は喜びにうちふるえ、天からは甘露の雨が降ったと
伝えられています。
今日でも四月八日はお釈迦様の誕生日、降誕会とも歓喜会とも称され、
誕生仏に甘茶をかけて拝むという行事が世界的に行われています。
天上天下唯我独尊とは「世間において私が最も優れた者である」
という意味で、これだけ見れば大変驕慢な言葉のようにも聞こえますが、
じつはこの言葉の後に「三(さん)界(がい)皆苦(かいく) 吾当安之
(ごとうあんし)」と続きます。
「この世の人生はみな苦である。私は苦しみ悩む人々に本当の安心を
与えてみせる」という意味です。
仏様の眼からみれば、どうでもよいいのちはなく、すべての命は尊い
からこそ、最も優れた安心を与えずにはおれないということでしょう。
坊守便り ー 花まつり ー
三年前の安泉寺宗祖親鸞聖人ご誕生800年・立教開宗750年・
本堂大屋根ご修復奉告法要に、たくさんのお子さん達が稚児行列に
ご参加下さいました。
稚児の衣装をまとった小さなお子さんたちが、僧侶の列の間に
加わって、お寺の周りを練り歩き、最後に本堂に入ってお焼香を
してくださいました。
以来、それをひとつの勝縁として続けて参りました花まつりを、
今年も行わせていただきます。
地域社会は縮小し、昔のように遊ぶ子どもの姿を目にすることも
減ってしまいました。
でもこの日ばかりは、すべて命は尊いとお教え下さる、お釈迦様
ご誕生のお姿をお祀りする花御堂をお花で飾り、甘茶を掛けて手を
合わせていただきます。
子ども達もお寺に楽しみに来てくれる日です。昨年秋より、
ご縁のあるサックス演奏の会の皆さんが、朝から爽やかな演奏を
聞かせてくださいます。
また「生野読み聞かせの会」の嶽さんが絵本と生野の民話を
ご披露下さいます。
そのほかにも境内でのスーパーボールすくいや、綿菓子作りなど、
子ども達に楽しんで頂きたいことです。
四月の行事
3 日(木) 午前10時半~ ピラティス
10日(木) 午前10時半~ ピラティス
17日(木)~20日(日)
大阪教区・難波別院 宗祖親鸞聖人ご誕生850年・
立教開宗800年慶讃法要
*20日に当寺より団体参拝いたします。
五月の行事
1 日(木) 午前10時半~ ピラティス
15日(木) 午前10時半~ ピラティス
17日(土) 午後2時~ 祥月講・同朋の会聞法会
ご講師 圓龍寺 門井 斉師
ハチドリのひとしずく
森が燃えていました。
森の生きものたちは、われ先にと逃げていきました。
でもクリキンディという名のハチドリだけは、
いったりきたり
口ばしで 水のしずくを一滴ずつ運んでは
火の上に落としていきます。
動物たちがそれを見て、
「そんなことをしていったい何になるんだ。」
といって笑います。
クリキンディはこう答えました。
「私は、私にできることをしているだけ」
青色青光
岩手県大船渡市で大規模な山火事が発生しました。何日も鎮火せず、
結局降雨を待たなければならなくなり、多くの山林や家屋が焼失しました。
特に東日本大震災の津波被害から、ようやく復興しつつあったところに、
このたびの山火事で二重に被災された方々もおられ、誠に痛ましい
ことです。
上記は南米アンデスに伝わる民話ですが、主人公のハチドリ
(英語名ハミングバード)は体長一〇センチにも満たない非常に小さい
鳥で、最小のマメハチドリなどは体重も2グラムしかなく、ホバリング
しながら花の蜜を吸って主食とし、その玉虫色の姿の美しさから
「飛ぶ宝石」とも言われています。
一度燃えさかると消すことの困難な山火事を、小さなハチドリの
くちばしからのひとしずくで、消すことなど到底かないません、が、
それでも自らに出来ることを精一杯尽くすその姿は、とかくどうせ
微力を尽くしたとて何も変わらないと諦める事を戒める物語です。
法蔵菩薩も師である世自在王仏から「あなたの立てた誓願は、大海の
水をすべて升でくみ取り、海底の宝を体をぬらさず手に入れるほどの
難事である。」と、諭されましたが、決して諦めず兆歳永劫のご修行
の末、ついに一切衆生を救わんという誓いを成就し、阿弥陀仏となられた、
だから我々はすでに救いに預かっているのだ、と説かれるのです。
住職日々随想
能登半島地震とそれに続く水害、大船渡の震災被害と山火事、
同じ地域を二度襲った災害に心痛みます。
まことに火も水も生活に不可欠なものですが、牙をむけば生活を根こそぎ
にしてしまいかねないものです。
七高僧のおひとり善導大師の「観経疏」に、『二河白道の比喩』が
あります。
善導大師はこの譬喩を通して、自らの人生を真に積極的に生き抜こう
とする決意が、いかなる状況にあろうとも、人間にとって何よりも大切な
ものであることを明らかにしておられます。
曰く、旅人がはるか西に向かって進み続けると、無人の茫漠たる広野に
到った。
すると忽然として眼前に、南に火の河、北に水の河が現れた。
それぞれ深さは底知れず南北両方にほとりはない、見ると中間に幅四、五寸、
長さ百歩ばかりの白い道が西の岸に続いている。
が、その道は時に火に焼かれ、時に水に飲み込まれ、と常に水火に侵され
ている。
そのうち後方から群賊や悪獣が、旅人を害そうとして追いかけてくる。
旅人は、引き返しても止まっても殺されてしまう、かといって前に進ん
でも水の河、火の河に落ちて死んでしまうだろう。
いずれにしても死は必定と、しばし逡巡した。
が「すでにこの道があるではないか」ならば前に進もう、と決意した
その時、東の岸から釈迦の「汝この道を行け、必ず死の難無けん」と
勧める声、また西の岸から「心を定めて恐れず直ちに来たれ。
我必ず汝を守護せん」と阿弥陀の呼び声が聞こえてきた。
ここに到って旅人は決然として、白道へ一歩踏み出した。群俗悪獣の
戻って来い悪いようにはせぬ、との声も振り切り、ついに西の岸、
極楽浄土に到り、善友と相まみえることが出来た、と。
慣用句に「怒りに身を焼く」「欲に溺れる」があります。
この二河白道の比喩で表される火の河は、衆生の瞋憎(しんぞう)・瞋恚
(しんに)(いかり・はらだち)水の河は貪愛(とんない)・貪欲(とんよく)
(尽きぬ欲望)を表しています。
怒りはカッとなって火が付き、燃えさかればついにはわが身をも焼き
尽くしてしまいます。
また水がじわじわとかさを増すように、むさぼりの心は、常にもっと
もっとと尽きることがありません。
じつに臨終の間際まで尽きることがないのが、この水火で表される
人間の根本煩悩なのです。
自らを省みる仏道に於いて、この根本煩悩と向き合い続けること、
それが念仏者の生活なのです。
真宗入門「お斎」
「お斎(とき)」とは、仏事の際にいただく食事のことを言います。
もともとは、古代インドで出家者が決まった時間(とき)に食事を
する事を「斎(とき)」と称していました。
これが後に転じて、仏事・法要などの折りにいただく食事どきに
「斎」の字を当てて、「とき」とよぶようになったのです。
歴史を遡ると、新たに僧侶になったときや、新しくご本尊や仏像を
お迎えしたときの法要で「お斎」が設けられてきた事が伺えます。
「お斎」は仏事・法要時の単なる会食でも宴会でもありません。
本願寺・第八代の蓮如上人は、日本全国を行脚し、布教に出向かれ
ましたが、お斎も大いに奨励されたということです。
上人はお斎を「合掌して如来・親鸞聖人の御用(おはらたき)として
いただく」とおっしゃっています。
仏祖のはたらきの中に生かされているという、そのご信心を
たしかめることにもつながる、「お斎」は大切な仏事のひとつなのです。
法語の味わい
ー法語カレンダー4月号よりー
天上天下唯我独尊
どうでもよい いのちはない
約二五〇〇年前の北インドで、お釈迦様はお生まれになられました。
誕生後すぐに七歩、歩かれ、天の上と下を指さし「天(てん)上(じよう)
天(てん)下(げ)唯(ゆい)我(が)独(どく)尊(そん)」と獅子吼されました。
その時に大地は喜びにうちふるえ、天からは甘露の雨が降ったと
伝えられています。
今日でも四月八日はお釈迦様の誕生日、降誕会とも歓喜会とも称され、
誕生仏に甘茶をかけて拝むという行事が世界的に行われています。
天上天下唯我独尊とは「世間において私が最も優れた者である」
という意味で、これだけ見れば大変驕慢な言葉のようにも聞こえますが、
じつはこの言葉の後に「三(さん)界(がい)皆苦(かいく) 吾当安之
(ごとうあんし)」と続きます。
「この世の人生はみな苦である。私は苦しみ悩む人々に本当の安心を
与えてみせる」という意味です。
仏様の眼からみれば、どうでもよいいのちはなく、すべての命は尊い
からこそ、最も優れた安心を与えずにはおれないということでしょう。
坊守便り ー 花まつり ー
三年前の安泉寺宗祖親鸞聖人ご誕生800年・立教開宗750年・
本堂大屋根ご修復奉告法要に、たくさんのお子さん達が稚児行列に
ご参加下さいました。
稚児の衣装をまとった小さなお子さんたちが、僧侶の列の間に
加わって、お寺の周りを練り歩き、最後に本堂に入ってお焼香を
してくださいました。
以来、それをひとつの勝縁として続けて参りました花まつりを、
今年も行わせていただきます。
地域社会は縮小し、昔のように遊ぶ子どもの姿を目にすることも
減ってしまいました。
でもこの日ばかりは、すべて命は尊いとお教え下さる、お釈迦様
ご誕生のお姿をお祀りする花御堂をお花で飾り、甘茶を掛けて手を
合わせていただきます。
子ども達もお寺に楽しみに来てくれる日です。昨年秋より、
ご縁のあるサックス演奏の会の皆さんが、朝から爽やかな演奏を
聞かせてくださいます。
また「生野読み聞かせの会」の嶽さんが絵本と生野の民話を
ご披露下さいます。
そのほかにも境内でのスーパーボールすくいや、綿菓子作りなど、
子ども達に楽しんで頂きたいことです。
四月の行事
3 日(木) 午前10時半~ ピラティス
10日(木) 午前10時半~ ピラティス
17日(木)~20日(日)
大阪教区・難波別院 宗祖親鸞聖人ご誕生850年・
立教開宗800年慶讃法要
*20日に当寺より団体参拝いたします。
五月の行事
1 日(木) 午前10時半~ ピラティス
15日(木) 午前10時半~ ピラティス
17日(土) 午後2時~ 祥月講・同朋の会聞法会
ご講師 圓龍寺 門井 斉師
New Article
Archive
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年11月
- 2024年9月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年3月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月